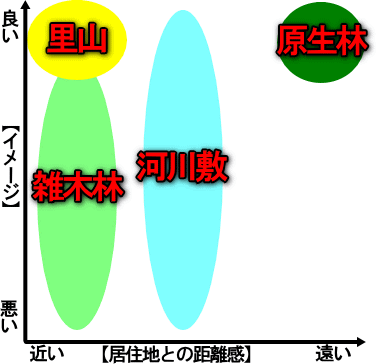
雑木林のイメージアップ作戦
採集に出かけるフィールドのうち、代表的なものに「里山」「雑木林」「河川敷」「原生林」がある。
実際は「雑木林」が「里山」を構成する風景の一部であることも多いが、
都会近くでは住宅地に雑木林がポツンと取り残されているので、一応別物として考えよう。
採集者にとって「雑木林」という言葉の響きが心地よいのは当然だが、ごく一般の人にとって、
これら4つの採集空間がどんなイメージで捉えられているかを考え、図に表してみた。
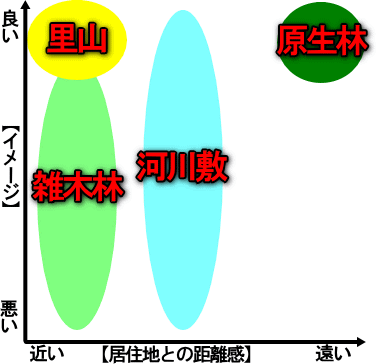
「里山」は近年の環境ブームの追い風もあり、かなり市民権を得ている言葉だ。
居住空間により近く(というより居住空間そのものが含まれ)、しかも好感度はダントツ。
生活の利便性にさえ目をつぶれば、人間が健康でストレスなく生きられる聖地のように思われている。
一方、「原生林」は人里離れた清らかな空間として、身近ではないがこれまたイメージがよろしい。
採集者にとってはミヤマ、ヒメオオ、小型種などの別天地で、一般の人にとっては、
たまに遠距離ドライブで紅葉狩りにいくような場所の代表格だ。
では「雑木林」はどうだろう。確かに居住地に隣接していて身近なフィールドには違いないが、
どうやらかなりマイナスイメージが定着している模様。
新聞の社会面に登場する「雑木林」は、いつも不法投棄が行われる場所であり、
身元不明の死体が発見されてしまう残念な場所なのである。
新聞は決して「**市内の里山で死体が発見された」とは書こうとしない。
「里山」は田畑、雑木林、屋敷林、小川などを含む総体だから、
具体的な位置を示す言葉として使われにくいのがその理由かもしれない。
里山は、「環境保護」や「自然と人間の共生」というスローガンのフラグシップモデルで、
決して汚してはならぬもの、という暗黙の了解が出来上がっているように感じる。
里山も雑木林も開発によって失われる被害者としては同じ立場のはず。
だが里山には「みんなで守りましょう」という意識が強く働き、雑木林は様々なひずみを
隠したり捨てる場所として、「やむをえず黙認しましょう」という感じになっている。
さしづめ、自然公園に置かれたゴミ箱といったところか。
「河川敷」は、雑木林同様にネガティブなイメージがあるいっぽう、野球やサッカーのグランドがあったり、
家族連れでレジャーを楽しめるなど、けっこう生活に潤いを与えてくれる空間として
明るく開放的なイメージも持ち合わせている。
◆
はたして雑木林のイメージアップは可能だろうか?
最近、こんな英語的表現による言い換えが目立つようになった。
清掃工場→クリーンセンター
霊園→メモリアルパーク
小手先といえばそうだし、見事といえば見事なまでにイメージが良くなっていることに気がつく。
雑木林も「エコ・フォレスト」だとか「ヒーリング(癒し)・ツリーズ」などと言い換えてしまえば、
「昨夜、**市のエコ・フォレストで死体が発見〜」などと書きづらくなり、
新聞記者も困りそうな気がしておもしろいのだが・・・。
![]()