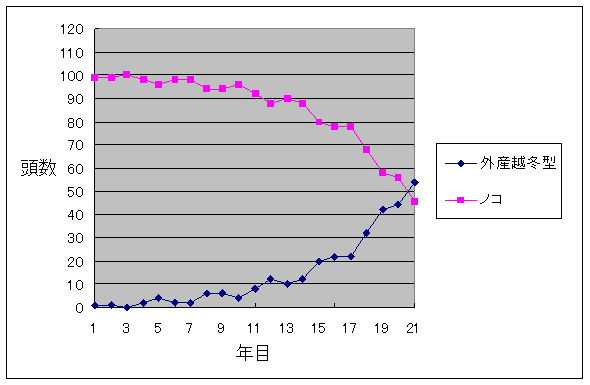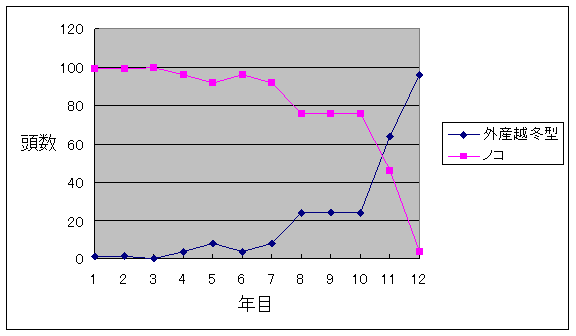①1ペアのクワガタはどう増えていく?
あるクワガタ(国産でも外国産でもよい)の♂と♀(1ペア)を飼育したとします。
昨今は飼育技術が確立されていますから、よほどブリードが困難な種を除いて
誰でも順調に累代を重ねていくことができます。
ここで、計算を単純化するために次のような条件を与えてみます。
①1ペアが1シーズンに産卵して誕生した幼虫のうち、10個体が次世代(F1)の
成虫になるものとする。
②成虫のうちオスとメスの比率は、1:1とする。
③温室環境で約1年で羽化。成熟期間を経て、メスは孵化から2年目に産卵する。
④メスは2シーズン続けて産卵をして死亡するものとする。
すると、飼育開始後の個体数は、右の表のように増加していきます。
仮に10ペア飼育する場合は、この数値を10倍すればいいわけです。
自力で飼育が困難になった分は、いわゆる「余品」とか「里子」という形で
引き取られたり、稀には放虫問題の当事者になる可能性もあります。
要は、自分の手を離れても全国の愛好者のあいだで増え続けていくわけで、
クワカブ趣味の裾野が広がり、市民権を獲得していくという好ましい状況のなか、
この現実をどう意識し、どう捉えるかです。
開発などにより自然環境が激減していくのに対して、全国の家の中には、
飼育ビンと温室という「良好で新しい環境」がどんどん作り出されているわけです。 |
|
個体数 |
| 1年目 |
2 |
| 2年目 |
2 |
| 3年目 |
10 |
| 4年目 |
20 |
| 5年目 |
60 |
| 6年目 |
150 |
| 7年目 |
400 |
| 8年目 |
1050 |
| 9年目 |
3750 |
| 10年目 |
7250 |
| 11年目 |
19000 |
| 12年目 |
50000 |
| 13年目 |
100000 |
|
②外国産のクワガタはどのくらいいる?
ある統計によると、2001年の1年間で外国産カブトムシが約31万個体、
外国産クワガタは約36万個体輸入されたそうです。
では、外国産クワガタに限って考えてみましょう。
36万個体のうち7割が購入されブリードされているとすると、その数は、
360000×0.7=252000個体です。
だいたいペアで購入しますから、126000ペアということになりますか。
これを①の表に当てはめて掛け算しますと、右の表のように増えていくことになります。
1年間の輸入個体数に限って考えても、9年後には、9億1350万個体に増加する
ことが予想されます。すごいですね。日本の人口は、約1億2千万です。
国民一人当たり、平均8個体も飼育している計算です。
また約4600万世帯あるので、1世帯当たり約20個体飼育していることになります。
願わくば、犬や猫のように世代や性別を超えたポピュラーなペットに昇格していれば
問題はないのですが・・・。
実際には、新規ブリーダー数も徐々に頭打ちになり、また交尾を自粛する人も増えるので
大丈夫、と楽観視できるかもしれませんが、少なくとも今後数年間は、諸事情で飼育できなく
なったり飽きてしまったりで、「殺すのもかわいそうだから林に逃がしてやろう」というケースも
徐々に増えていくことは間違いありません。
ヤマトさんのHPコンテンツ「森へ放すの?ちょっと待った!」を読むと、飼育していた虫を
自然に帰すことは決して虫を救うことにはならない、ということがよくわかります。
|
|
個体数 |
| 2001年 |
252000 |
| 2002年 |
252000 |
| 2003年 |
1260000 |
| 2004年 |
2520000 |
2005年
|
7560000 |
| 2006年 |
18900000 |
| 2007年 |
50400000 |
2008年
|
132300000 |
2009年
|
472500000 |
2010年
|
913500000 |
| 2011年 |
2394000000 |
| 2012年 |
6300000000 |
| 2013年 |
12600000000 |
|
③自然界のクワガタの累代サイクルは?
まず、住宅地に囲まれた野球場ほどの雑木林を想定します。
越冬タイプのコクワやヒラタの累代は、①の表を3年サイクルにすればいいのですが
自然界は飼育環境と違い成虫になる生存率が低く、爆発的に増えることはありません。
ここでは話を単純化するために、この雑木林はノコギリクワガタだけが棲息しているものとし、
その個体数(成虫)は、100とします。
また、生態系が安定していて毎年、100より減ることもなく増えることもないものとします。
人間の採集圧は無視します。この林のノコはいったいどんなサイクルで世代交代を
行っているのでしょうか? 大雑把に言うと右表のようになっていると思われます。
温室ではなく屋外ですので、世代交代の期間は3年とみていいでしょう(右図の黄色)。
仮に2003年夏にノコを乱獲すると2006年夏にグンと減ってしまいますが、赤・緑のグループ
のローテーションで生き残るので絶滅はしません。
が、3年間乱獲が続くとちょっと致命的です。
また、3年後に同数の成虫が見られるということは、50頭の♀から100頭成虫が誕生
することになります。1頭の♀につき2頭の成虫です。仮に♀1頭あたり平均10個産卵
したとすると成虫までの生存率は2割という計算になります。
|
| ノコの変態サイクルモデル |
|
成虫個体数 |
♀の
個体数 |
変態
|
| 2003年夏 |
100 |
50 |
卵 |
| 2004年夏 |
100 |
|
幼虫 |
| 2005年夏 |
100 |
|
蛹 |
2006年
夏 |
100 |
50 |
成虫 |
| 2007年夏 |
100 |
|
|
| 2008年夏 |
100 |
|
|
|
④もし外国産のクワガタが放されたら?
仮に、たった1頭の外国産(仮にAとする)が、③のようなノコ100頭だけの雑木林に放されたと
します。もちろん、日本の気候に適応できる種であるとします。
この個体は、下表の6タイプのうちいずれかのはずです。
| 放された外国産Aの条件(1個体の場合) |
発生する次世代個体は? |
| 外国産純血種 |
交雑種 |
| ①日本産との間に繁殖能力がある♂ |
× |
○ |
| ②日本産との間に繁殖能力がない♂ |
× |
× |
| ③日本産との間に繁殖能力がある♀(交尾済) |
○ |
○ |
| ④日本産との間に繁殖能力がある♀(未交尾) |
× |
○ |
| ⑤日本産との間に繁殖能力がない♀(交尾済) |
○ |
× |
| ⑥日本産との間に繁殖能力がない♀(未交尾) |
× |
× |
②と⑥以外は子孫を残すという意味で、生態系へ長期的な影響を及ぼすおそれがあり、
「たった一匹ぐらいいいじゃん」という考えは危険でしょう。
では、上表の⑤のケース、つまり「日本産との間に繁殖能力を持たない♀が
1頭だけ雑木林に放された場合」にどうなるか考えてみたいと思います。
【シミュレーションの条件】
①外国産Aは越冬タイプとし、その次世代生存率はノコと同じように、2割(10個産卵して
2頭成虫になる)とする。
②この雑木林におけるクワガタのキャパシティは、100頭を限界とする。
③外国産Aとノコの縄張り争いにおいては、外国産Aが勝つものとする。
(ここでは「外国産が1頭増えるとノコが1頭減る」ものとして計算)
|
|